2025年08月28日
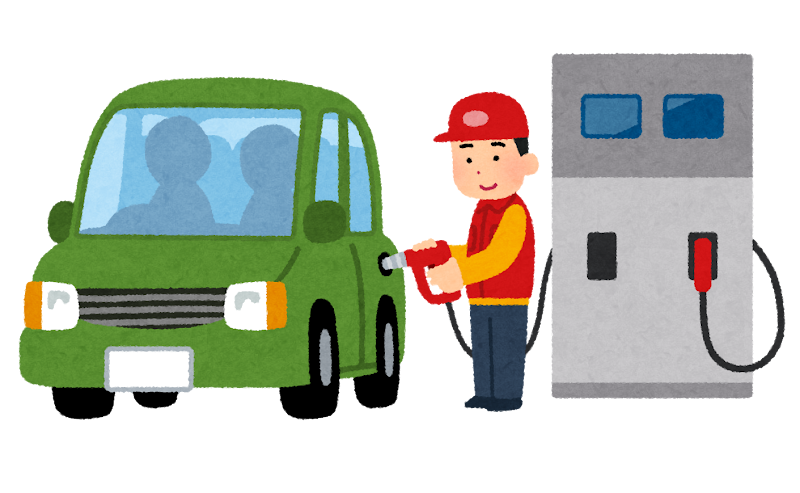
ガソリン暫定税率の廃止と走行税導入による様々な業界への影響
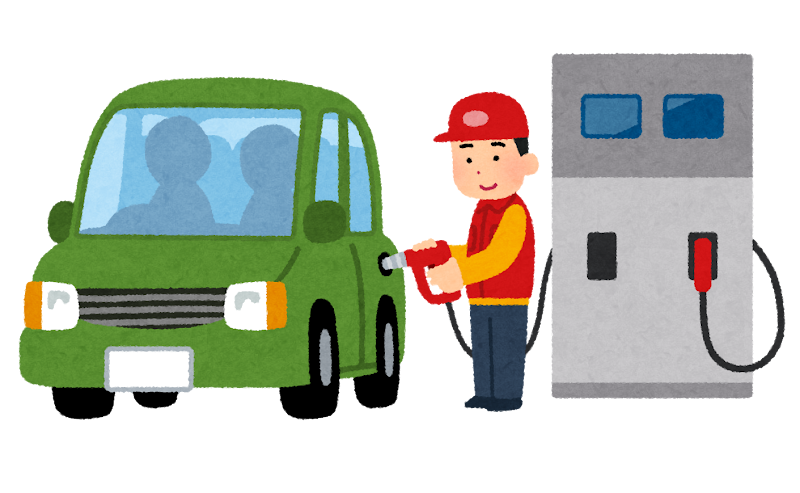
2025年8月の臨時国会において提出されたガソリン暫定税率廃止法案ですが早ければ11月にも施行されます。
では実際にガソリン暫定税率が廃止され、その代替財源として走行距離に応じて課税される「走行税」が導入された場合、多くの業界に大きな影響が及ぶと予測されます。その業界はどこなのか、恩恵を受ける業界はどこなのか、簡単ではありますがまとめてみました。
弊害・損害を受ける業界
運輸・物流業界:コスト増が経営を直撃
運輸・物流業界は、走行税導入による最も深刻な影響を受ける業界の一つです。
- コストの直接的な増加: 事業の根幹であるトラックや配送車の走行距離そのものが課税対象となるため、税負担が企業の収益を直接圧迫します。長距離輸送が中心となる事業者ほど、その影響は甚大です。
- 運賃への転嫁と消費への影響: 増加したコストを運賃に転嫁せざるを得ない場合、最終的に商品価格に反映され、物価全体を押し上げる要因となり得ます。これにより、消費者の負担が増加し、景気の冷え込みにつながる懸念があります。
- 中小企業の経営圧迫: 体力のある大手企業に比べ、価格競争力が弱い中小の運送事業者にとっては、コスト増が死活問題となり、業界全体の構造変化を招く可能性も指摘されています。
自動車業界:消費者のマインド変化
自動車の「所有」から「利用」への価値観の変化を加速させる可能性があります。
- 購買意欲の減退: 走行距離が長いユーザー、特に地方在住者や営業職など日常的に車を使う人々にとって、維持費の増加は大きな懸念材料です。「走れば走るほど税金がかかる」という仕組みは、自動車の購入をためらわせる要因になり得ます。
- 市場ニーズの変化: 長距離の利用を前提とした大型車やファミリーカーの需要が減少し、近距離移動に適した小型車や軽自動車へのニーズが高まる可能性があります。
- EVシフトへの影響: これまでガソリン税の負担がないことが大きなメリットだった電気自動車(EV)も課税対象となるため、EVへの移行インセンティブが薄れ、普及のペースが鈍化する可能性が懸念されます。
観光・レジャー・小売業界:人の流れが変わる
移動コストの増加は、人々の行動範囲に影響を与えます。
- 観光業への影響: マイカーでの長距離旅行が敬遠され、遠隔地の観光地にとっては客足が遠のく要因となり得ます。一方で、公共交通機関でアクセスしやすい都市部や近場の観光地が選ばれる傾向が強まる可能性があります。
- 郊外型店舗への影響: 自動車での来店を前提とする郊外の大型ショッピングセンターやロードサイド店舗は、来店客数の減少という形で影響を受ける可能性があります。
レンタカー・カーシェアリング業界:料金体系の変更
- コスト増の価格転嫁: 走行税は、事業者が所有する車両の走行距離に応じて課税されるため、運営コストが直接的に増加します。この増加分は、ほぼ確実に利用料金に上乗せされることになるでしょう。
- 「距離従量制」料金の導入: 現在の「時間料金+距離料金」という体系から、走行距離に応じた課金の比重がさらに高まる可能性があります。これにより、利用者は走った分だけ料金を支払うという、より分かりやすい形になりますが、長距離の利用者にとっては実質的な値上げとなります。
- 短距離・短時間利用へのシフト: 利用料金の値上げ、特に長距離利用での割高感から、利用者は「ちょっとした移動」や「近場での利用」に用途を限定する傾向が強まる可能性があります。これまでのように、レンタカーで長距離の旅行をするという利用スタイルは減少するかもしれません。
- 利用頻度の減少: 全体的なコスト増により、これまで手軽に利用していた層が、利用をためらうようになる可能性があります。特に、レジャー目的での利用が影響を受けやすいと考えられます。
- ビジネスモデルの見直し: 長距離利用者の減少を見越し、都市部の短距離移動ニーズに特化したり、公共交通機関との連携を強化したりするなど、事業戦略の見直しを迫られる可能性があります。
- 車両の構成の変化: 燃費の良い小型車や電気自動車(EV)の比率を高める動きが加速するかもしれませんが、走行税はEVも課税対象となるため、税負担の軽減効果は限定的です。
恩恵を受ける業界
国や地方自治体 ️
最大の受益者は、税金を徴収する国や地方自治体です。
- 安定した財源の確保: 電気自動車(EV)やハイブリッドカーの普及により、ガソリン税の税収は将来的に減少していくことが確実視されています。道路の維持管理費などはこのガソリン税でまかなわれているため、それに代わる安定的な財源として走行税が検討されています。車の燃料に関わらず、走行距離に応じて課税することで、税収を確保しやすくなります。
自動車をあまり利用しない人 ♀️
- 公平性の実現(応益負担): 走行税は「道路を多く利用する(=長く走る)人ほど多くの税金を負担する」という「応益負担」の考え方に基づいています。
- 週末しか運転しないサンデードライバー
- 近所の買い物程度にしか車を使わない人
- 公共交通機関が発達した都市部に住み、車の利用頻度が低い人
こういった人々にとっては、現在の自動車税のように「所有しているだけ」でかかる税金の負担が減り、実際に利用した分だけを支払うことになるため、税負担が軽くなる可能性があります。
環境負荷の低減を重視する考え方
間接的なメリットとして、環境負荷の低減につながるという見方もあります。
- 走行抑制効果: 走行距離に応じて課税されることで、人々が不要不急の車の利用を控えるようになる可能性があります。これにより、交通量が減少し、渋滞の緩和やCO2排出量の削減といった効果が期待されます。
最後に
今回導入が予定されている走行税は、「税の公平性」と「安定した財源確保」という2つの大きな目的を持った施策です。そのため、恩恵を受けるのは主に政府と、車を所有していてもあまり長距離を走らない人々ということになります。
一方で、通勤や生活のために長距離を移動せざるを得ない地方在住者や、運輸・物流業界にとっては、負担が大幅に増えるデメリットの大きい施策と言えます。
The following two tabs change content below.


今関商会
取締役 : 株式会社今関商会
1952年創業の今関商会の三代目。
大学卒業後、出光興産(株)の東海支店にてガソリンスタンドの現場から販売促進課、工業用潤滑油課、販売店担当などを経て退社。
2013年より、実家である(株)今関商会に入社。
趣味はNFL鑑賞と筋トレ
2児の父でもあります。
会社ではSS現場やブログ、Facebook、instagram等、SNSの更新も行っています。
最新記事 by 今関商会 (全て見る)
- ガソリン暫定税率の廃止と走行税導入による様々な業界への影響 - 2025年8月28日
- 梅雨に負けるな!フロントガラスに鱗落とし&ガラスコートで快適運転!! - 2024年6月18日
- 猛暑になる前に自動車のエアコンガスクリーニングで快適&燃費改善! - 2024年6月10日
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。
- トラックバック URL
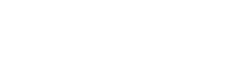
この投稿へのコメント